| HOME | 懸造りコレクション | 懸造り一覧(都道府県別) | 懸造り一覧(宗教別) |
|---|---|---|---|
| 懸造り訪問履歴 | 懸造りランキング | 懸造り用語集 | 古文書・古画集 |
| 真田氏と懸造り | 掲示板 | 参考文献、リンク集 | 更新履歴 |
| 番外編:仏塔 | 番外編:さざえ堂 | 番外編:天守 | 番外編:湯屋 |
懸造り用語集
◆ 造語(当サイトの独自用語) |
|||||
| 用語 | よみ | 説明 | 懸造り例 | ||
|---|---|---|---|---|---|
懸造り部 |
かけづくり・ぶ | 平地ではない斜面に、長さの異なる束柱を立ち上げ、梁や貫なども使って、その上が水平になるようにした木組みの部分。 | 全部 | ||
上屋部 |
うわや・ぶ | 懸造り部の上に建てられた建物、堂宇。 |
苗木城跡 赤城神社 岩谷観音 (青森県中津軽郡西目屋村) 乳穂ヶ滝 大嶽山那賀都神社 千栄殿 江之浦測候所 光学硝子舞台 を除く全部 | ||
懸崖型 |
けんがい・がた | 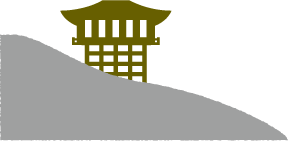 自然懸崖の地面に柱を立ち上げた懸造りの様式。
自然懸崖の地面に柱を立ち上げた懸造りの様式。懸造りが斜面に立てられていても、石垣やコンクリートなどにより整地されている場合は、呼ばない。 |
多数 | ||
舞台型 |
ぶたい・がた | 立ち上げた柱の上が広い床状になっており、上屋が乗っていない部分の様式。すなわち、舞台状になっていること。 |
清水寺 本堂 清水寺 奥の院 寛永寺 清水観音堂 清水寺 救世殿 (新潟県佐渡市) 長谷寺 本堂 薬王院 岩出観音 羅漢寺 千体地蔵堂 赤城神社 浅間山観音堂 競秀峰 妙見窟 普光寺 護摩堂 乳穂ヶ滝 大嶽山那賀都神社 千栄殿 Y邸 江之浦測候所 光学硝子舞台 | ||
投入型 |
なげいれ・がた | 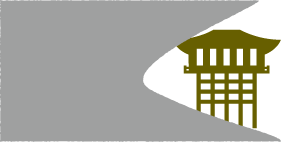 自然懸崖に木造柱を立ち上げた懸造り部があり、その上に乗っている上屋には、更に自然懸崖が天蓋のように、全体に覆い被さっている様式。雨が降った場合、上屋部も懸造り部も濡れないことになる。
自然懸崖に木造柱を立ち上げた懸造り部があり、その上に乗っている上屋には、更に自然懸崖が天蓋のように、全体に覆い被さっている様式。雨が降った場合、上屋部も懸造り部も濡れないことになる。最も代表的な建物が「三徳山 三佛寺 投入堂」であり、岩屋内に建物を下から投げ入れたような伝承があることから、こう呼ぶ。 |
日本三大投入堂 三徳山 三佛寺 投入堂 不動院岩屋堂 龍岩寺 奥院礼堂
滝沢観音石仏群 大日堂 「群馬の投入堂」 | ||
凸型 |
とつ・がた | 懸造り部を上から見た際の形状が、凸状になっている様式。 舞台型は凸型になることが多い。 |
清水寺 本堂 西方寺 普明閣 北向観音 薬師堂 長谷寺 本堂 薬王院 清明亭 瀧水寺 観音堂 普光寺 護摩堂 | ||
滝裏型 |
たきうら・がた | 全国には稀に滝を裏側(滝壺の奥)から見られるところがあり「裏見の滝」などと呼ばれるが、それが懸造りの上から見られる。 |
乳穂ヶ滝 鰐淵寺 蔵王堂 | ||
宇宙船型 |
うちゅうせん・がた | SF映画『未知との遭遇』や『スター・ウォーズ』に出てくるような宇宙船は、地面に着陸すると、宇宙船の両足の間からタラップが下りてくるタイプが多い。離陸時には逆にそこを登って船内に入ることになるのだが、正にそのような感じで、床下へ通じる階段が付いた堂宇が稀にある。 |
肬水神社 東屋神社 岩谷観音 (青森県中津軽郡西目屋村) | ||
割拝殿型 |
わりはいでん・がた | 神社の社殿の様式の一つに割拝殿というものがある。本殿・拝殿に至る参道を跨ぐように立つ建物だが、中央部がくり抜かれていて、土足のまま内部を通過できるようになっている。神楽殿を兼ねている場合も多い。それが懸造りとなると、石段を登って、床下から潜り抜けていくような感じになる。 |
清水寺 山門 日枝神社 神楽殿 鹿島神社 割拝殿 護国寺 不老門 山田神社 楼門 篠井神社 神楽殿 由岐神社 拝殿 名草神社 拝殿 | ||
清水系 |
きよみず・けい | 懸造りのある寺社のうち、縁起、由来が京都市東山の「音羽山 清水寺」に関連する寺社で、名前に「清水」と付くか、読み方に「きよみず」か「せいすい」と付く寺社の総称、流派。 本家「清水寺 本堂」が懸造りであることから、それを模して懸造りとなることが多い。 本家「清水寺」と同じく、千手観世音菩薩を本尊とすることが多い。 |
清水寺 本堂 清水寺 奥の院 寛永寺 清水観音堂 多賀神社(清水観音堂) 清水寺 山門 (群馬県高崎市) 清水寺 救世殿 (新潟県佐渡市) 清水寺 観音堂 (長野県長野市) 清水山公園 展望台 小石川後楽園 清水観音堂跡 清水展望台跡 | ||
準清水系 |
じゅん・きよみず・けい | (1) 懸造りのある寺社のうち、縁起、由来が京都の「音羽山 清水寺」に関連する寺社で、名前に「清水」や、読み方に「きよみず」「せいすい」と付かない寺社の総称、流派。
(2) 懸造りの印象が先行して、京都の「音羽山 清水寺」の別地方版と呼ばれるような寺社の総称、流派。「音羽山 清水寺」の流れを組む訳でもなく、直接的な関係はないと思われる。 |
(1) 唐松観音堂 達谷窟毘沙門堂 浅間山観音堂 厄除観世音 長源寺 弁天堂
(2) | ||
長谷系 |
はせ・けい | 懸造りのある寺社のうち、縁起、由来が奈良初瀬の「豊山 長谷寺」に関連する寺社、もしくは名前に「長谷」と付くか、読み方に「はせ」か「ちょうこく」と付く寺社の総称、流派。 本家「長谷寺 本堂」が懸造りであることから、それを模して懸造りとなることが多い。 本家「長谷寺」と同じく、十一面観世音菩薩を本尊とすることが多い。 |
長谷寺 本堂 護国寺 不老門 薬王院 「東長谷寺」 大久山 長谷寺 打吹山 長谷寺 清水寺 救世殿 (新潟県佐渡市) | ||
稲荷系 |
いなり・けい | 懸造りのある寺社のうち、名前に「稲荷」と付く神社の総称、流派。 理由は定かではないが、懸造り神社に「稲荷」が多いのは、一般的に稲荷の数が多いだけか。 |
鼻顔稲荷神社 山内稲荷社 竹山随護稲荷神社 豊川稲荷神社 草戸稲荷神社 祐徳稲荷神社 臼田の稲荷神社 神楽殿 根津神社 乙女稲荷 | ||
善光寺系 |
ぜんこうじ・けい | 懸造りのある寺社のうち、縁起、由来が長野市の「定額山 善光寺」に関連する寺社の総称、流派。 ちなみにその本家である善光寺には、残念なことに懸造りはない。 |
北向観音 薬師堂 布引観音 ブランド薬師 活禅寺 法国山 阿弥陀寺 岩屋善光堂 報恩寺(善光寺) 岩屋観音堂 | ||
伊達系 |
だて・けい | 戦国時代の東北の覇者伊達家は、代々懸造り好き。 山形県米沢市と宮城県内の伊達家の居城だったお城に懸造りがあったといわれるが、現存するものはない。寺院では二箇所現存している。 |
仙台城 懸造跡 (現存せず) 勝画楼 達谷窟毘沙門堂 米沢城(現存せず) 舘山城(現存せず) 岩出山城(現存せず) 角田城(現存せず) | ||
◆ 建築用語(主に、木造の日本建築) |
|||||
| 用語 | よみ | 説明 | イメージ | ||
貫 |
ぬき | 垂直に建ち並んだ束柱の幹に穴を開け、そこへ木材を水平に通したものが貫。床下部分の補強に使われるため、懸造り建築では多用される。 |

| ||
入母屋造り |
いりもや・づくり | 長方形の建物の四面を葺いた屋根。切妻屋根の短辺側に庇を付けたような形。屋根の勾配は下に降りるほど緩やかになることが多い。寺院やお城に多用される。 |

| ||
切妻造り |
きりつま・づくり | 長方形の建物の長辺側二面を「へ」の字型に葺いた屋根。屋根の勾配は直線になることが多い。神社の社殿に多用される。 |

| ||
寄棟造り |
よせむね・づくり | 長方形の建物の四面を葺いた屋根。長辺二面の台形、短辺二面の三角形を組み合わせた形。 |

| ||
宝形造り |
ほうぎょう・づくり | 四面を葺いた屋根。建物の中央を頂点とした三角形を四面に配した形。屋根の勾配は下に降りるほど緩やかになることが多い。 |

| ||